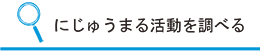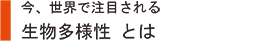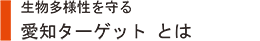生物多様性条約とは
生物多様性条約は、正式名称「生物の多様性に関する条約(Convention on Biological Diversity、英語略称:CBD)」といい、1992年5月22日採択、1993年12月29日発効された国際条約です。ブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際連合会議」(通称、地球サミット)で採択された気候変動枠組み条約と並ぶ双子の条約と呼ばれ1 、地域共同体であるECを含む、196の国と地域(2015年7月現在)2 が加盟しています。加盟すれば自国の自然・文化を世界遺産リストに推薦できる世界遺産条約の加盟国数186カ国(2009年4月16日)より多くなっています。
条約の目的として、生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の公正・衡平な配分という3つが掲げられ、条約に加盟している国(締約国)は、2年に1度開催される締約国会議(Conference of Parties、略称:COP)にて、条約の目的達成に必要な事項を、コンセンサス(全加盟国の総意)で定めてきました。
また、第19条3項に基づいて、遺伝子組換え生物の規制に関する検討がなされ、2000年に特別締約国会議(Ex-COP)を開催し、「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」を採択し、以降、条約本体の締約国会議と連続して議定書署名国による会合(BS-MOP)を開催しています。
2010年愛知県名古屋市で、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(通称、名古屋議定書)」が採択され、議定書発効要件である50カ国の批准を2014年7月10日になされたことから、2014年10月12日(第12回締約国会合期間中)に、正式に発効し、第1回名古屋議定書締約国会合(NP-MOP1)が開催されました。
生物多様性条約本文(和訳)
http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html
生物多様性条約解説(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
カルタヘナ議定書本文
http://www.bch.biodic.go.jp/gitei2.html
カルタヘナ議定書解説(バイオセーフティ クリアリングハウスメカニズム)
名古屋議定書本文(日本は、2014年10月段階で批准していないため、外務省仮訳)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/shomei_72.pdf
名古屋議定書に関するサイト
http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/conf01.html
1 同じく、地球サミットにて取り上げられた「砂漠化防止条約」を含めてリオ3条約と呼ばれることもある。
2 非加盟国は、アメリカ、バチカン市国
生物多様性条約の背景
生物多様性条約の理念を示す前文は長く、全23段落に及びます。そこからもわかるとおり、いくつもの社会的背景の中でこの条約が必要とされ生まれてきたといえます。「遺伝子資源の保護」と先進国と発展途上国の関係いわゆる「南北問題」も大きな要素の一つです。
<1970年代>
1970年代、環境の時代と呼ばれるこの時代には、湿地の保護をうたった「ラムサール条約」、貴重な文化・自然の保護のための「世界遺産条約」、国際取引による絶滅を防ぐための「ワシントン条約」、移動性動物の保護を目的として「ボン条約(日本未批准)」が生まれました。一方で、1975年には世界の科学者によるアシロマ会議(米国)で「組み換えDNA実験のガイドライン」策定されるなど、「遺伝子の有用性と技術利用の危険性」が認識されたのもこの時代です。熱帯雨林の伐採や大型インフラ整備事業による自然破壊を止めることの意義に(将来の利用も含めた)遺伝資源の保護が加わりました。
<1980年代 生物多様性条約の萌芽>
国際的なNGOや日本自然保護協会といった全国レベルのNGO、各国政府機関が加盟するIUCNでは、1982年に開催された第3回世界公園会議において、「天然遺伝資源の保護」を進めることを決議し、商業的な天然遺伝資源の収奪を規制する手法にどのようなものが考えられるか研究すること始めました。遺伝資源の保護の手法を検討すると当然の帰結として包括的な手法をとらざるを得ません。ラムサール条約のようにある生態系を限定して守る手法では不十分です。世界には多様な生態系が存在し、「将来どんな価値を持った遺伝資源が見つかるか」は誰にもわからないからです。同じような理由で国際取引を規制しても意味がありません。つまり、遺伝資源の保護とは、将来の価値を損失しないように守る、すなわち、今ある生物や生物のつながりのもつ多様性さ(=生物多様性)をそのままに守る、あるいは持続可能な仕方で利用することになります。
もう一つ生物多様性条約を特徴付けるのは、世界全体で生物多様性を守ろうといったときに、すでに経済発展を果たし、さらには他国の自然資源を利用して経済を成り立たせている「先進国」と、これからの経済発展に期待し、自国に豊かな生物多様性を残す「発展途上国」との間の立場の違いです。豊かな生物多様性を有する発展途上国がこれからも自国の多様性を守っていくための動機付けを持つためにも、発展途上国が守り続けた生物多様性を先進国が一方的に利用し、利益を得ることは許されません。このような考え方から、生物多様性条約の第三の目的である遺伝資源から得られる利益の公正・衡平な配分(ABS)が生まれました。
この立場を担保するためにも条約の第15条1項では「各国は、自国の天然資源に対して主権的権利を有するものと認められ、遺伝資源の取得の機会につき定める権限は、当該遺伝資源が存する国の政府に属し、その国の国内法令に従う。」と定め、先進国が“勝手に”遺伝資源を発展途上国から持っていくことがないよう、発展途上国に取得に関する権限を認めています。生物多様性条約は、経済に関する条約ともいえます。
生物多様性条約の取り組み
生物多様性条約は、どのような影響力をもった条約なのでしょうか。一言で言えば、生物多様性条約は、世界レベルのルールや基準、目標(方向性)を決める力を持っています。
生物多様性条約のツールの一つに、締約国会議で合意される決議があります。決議の中には世界レベルの行動目標や指針等を決めることがあります。2002年に採択された生物多様性条約戦略計画(2002-2010)では、「生物多様性の劣化速度を顕著に減少させること」を全体目標に掲げ(通称2010年目標)、多様な主体の参画や新しい資金メカニズムの検討、詳細な数値目標の設定などを進めています。この目標は、ヨハネスブルクサミットやミレニアム開発目標にも採用され、地球レベルの環境政策の指針になりました。
ほかにも、2004年に採択された侵略的外来種に関する決議は、日本の特定外来生物法(正式名称、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の成立に大きな影響を与えました。条約の下には「カルタヘナ議定書」が作られており、この議定書発効を受けて日本もカルタヘナ法(正式名称、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)が作られています。
生物多様性条約のツールの2つ目に、条約加盟国に策定が義務付けられている「生物多様性国家戦略・行動計画」があります。2014年10月時点で、179カ国が策定し、そのうち45カ国が改定をしています。この中で、各国は、環境省などの一省庁だけでなく政府全体で生物多様性の保全や持続可能な利用にむけた取り組みを進めなければなりません。最近注目を浴びている「里山」の取り組みは、日本自然保護協会等のNGOの後押しもあり、第2次戦略(新・生物多様性国家戦略)で大きく取り上げられたことがきっかけです。
三つ目は、フォーラムとしての条約の役割です。2年に1度開催される締約国会議は、参加者が増加傾向にあり、COP10では、7000人の参加者がありました。締約国会議の参加者は政府のみならず、メディア、企業、研究機関、NGO、先住民族、ユースなど年々多彩になっており、最新の自然保護の動向や新しい取り組みなどを交流する場ともなっています。生物多様性条約は、言い換えれば「人と自然の関係性」を扱う条約ですので、関係しない分野は存在しないともいえるのです。
生物多様性条約第10回締約国会合(COP10)
生物多様性条約の位置づけを変えた歴史的な会議は、日本で開かれました。2010年愛知県名古屋市で開催された「第10回締約国会合(COP10)」です。世界各地から7000人以上、周辺イベントも含めると11万人が参加したこの会合では、2011年から2020年までの生物多様性戦略計画および愛知ターゲットを193カ国でまとめあげたほか、先進国と途上国で対立の多かった「遺伝資源へのアクセスとその利用から得られる利益の公正公平な配分に関する追加ルール「名古屋議定書」を作り出しました。
愛知ターゲットは、日本の市民の提案が実り、生物多様性条約だけの目標ではなく、国連全体の目標として提案することも決まり、COP10の直後の2010年12月の第65回国連総会にて、2011年から2020年を「国連生物多様性の10年」と宣言し、国連全体で愛知ターゲット達成に向けた行動を促すことが決まりました。